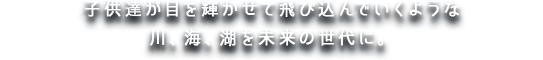CWPブログ
- 2025/09/12
-
「森と川と人をつなぐ楽校」川と足元、生き物をじっくり見よう!
執筆者: 岡本亮太 (たんたん)

じっくり。じっくり。
つかまえた!生き物捕まえた!という、あの興奮から、その先にある「その生き物こと、じっくり見てみよう」をやりました。
加えて、足元もじっくり見てね。川の周りもじっくり見てね。そう、この日のテーマは「じっくり」
捕まえるだけでは、わからない、生き物の姿や不思議を、じっくり見つめます。

この日は、午前中は川に行って、川を、川の中を、じっくり見つめることで、生き物を探すことと、ごみを拾うことをやりました。
なぜ、ごみ?
WORLD CLEANUP DAY(WCD)のイベントとしての意味を持って開催したからです。
WCDとは、簡単に言うと、エストニア発祥の『年に1度は世界中でごみ拾いしようぜ』ということで、毎年9月がその期間です。
わたしたちClearWaterProjectは、WCDのパートナーとして活動していることもあり、9月に今回の内容を企画しました。

おとなも、こどもも、みんな、じっくりと川を見つめて、たくさんの川ごみを拾ってくれました。
ごみの話は、午後につづきます。
午前のガサガサのはなしをもうちょいします。
これが、この日とれた生き物たちをまとめた水族館です。
この水族館を「じっくり」見ると、気づくかもしれません。
『なんだか小さい魚が多い気がするなあ』って。その気づき、参加者の方からも挙がった声です。
この川では、6月にもガサガサをやりました。あのときは「たくさん」をテーマに、生き物をつかまえました。↑6月の様子 さて、9月のこの時期に、なぜ、小さい魚が多いのでしょう?
6月に参加してくれた人は、ハッと!なるような感覚があったようにも見受けられました。
あの時は卵だったのが、夏の間に孵って泳いでいるからだ!6月のときには、実際に魚の卵を見てもらうことができましたので、時間がつながり、ストーリーになった瞬間でした。
じゃあ、なぜ生き物は、夏の間に孵るのだろう???
そんな問いかけも、楽しみました。
箱メガネで「じっくり」と、水中をのぞく彼の、この日の一番たのしかったことは、この箱メガネでカマツカを見ることができたこと。
彼は、6月に、この川でカマツカを捕まえることが、できたのです。
もしかしたら、捕まえることのほうが喜びは上なのかもしれないけれど、こうやって「じっくり」見ないと、泳いでいる”本来の”カマツカの姿は見られないかもしれません。
そう思うと、もしかしたら捕まえるということ以上に、彼自身が自分でがんばって探したことにより、貴重な機会となったのかもと思います。
こうやって、親子で水槽を、水族館を、今日の成果を見つめる姿、うれしいですね。
子どもとの時間って、あるようで、実は人生の中でも少ないのかもしれません。こうやって、子どもと一緒に、あるいは親と一緒に、その日を全力で楽しんで、捕まえた生き物を「じっくり」見る。
この時間は、プライスレス。
計り知れない価値があるんじゃないかなって思います。
あのとき一緒に川に行ったよね。
その記憶が、いつまでも残り、捕った時に感じた想いや気づきを、この先も親子の会話のタネにしたり、いつも一番身近にいる人同士でも、見る、感じる、気になったポイントや視点が違うことを通して、なにか環境や水について考えるきっかけになったりすると、とてもうれしいなって思います。親子で協力して楽しめるのも、ガサガサの魅力です。
網を構えて、足で蹴って、網に入った生き物を確認する・・・
ひたすらに続く、その繰り返しの中に、たくさんの喜びや、残念や、興奮が詰まっています。
毎回、網をあげて、網の中を「じっくり」見つめると、ぴちぴちと躍る姿。ぴょんぴょん跳ねる姿。じっととどまる姿。いろんな生き物に出会えます。
親子で一緒に、興奮し、生き物に会いたいと願う姿を見ると、川を大事に、生き物を守ろう、そういうこっちが持っているメッセージを、直接言葉にしなくても、わかってもらえているような気がします。そう思うと、ガサガサというのは、すごい遊びだなって、この日も思いました。
生き物が入っていますようにと、すくいあげる、その網の中には、願いや想いや、いろんなものがつまっている。そんな気がします。

『さあ、このさかな見てみよう』
なんで、こんな色しているの?
なんで、ごつごつしているの?
なんで、このさかなだけなの?「じっくり」見つめることで、生き物の不思議を深堀していきます。

家族にひとつ、魚を入れた観察ケースを渡します。
『魚のひれ、どこに、いくつある?』
『どじょうのひげ、何本ある?』
『魚の耳って、どこにある?』いろんな質問を投げかけるたび、親子で、観察ケースに入った生き物を眺めます。

「じっくり」見なければわからないことばかり。
ときに、「じっくり」見てもわからないのが、生き物の不思議。なんで、「じっくり」っていうテーマにしたのか。
それは、生き物に興味を持ち、知る、ということを深めてほしかったから。
生き物には不思議がいっぱい、というよりも、不思議しかないかもしれません。例えば普段食べている焼き魚だって、刺身だって、泳いでいる姿やその生態は知らないかもしれません。
それが『魚であること』は、知っています。魚であるさかなが、どんな生き物なのか、を知れば、もっと興味を持ってもらえる、そして、そんな魚たちを取り巻く環境が、どんなことになっているのか、にも関心を深めてもらえる、そう思っての企画です。
さて、午後は、屋内で、ごみを用いたアップサイクル体験です。
午前中に、川でたくさんのごみを拾ってくれました。
そうやって拾ってくれることで、海までたどり着かないようにできて、海ごみになることを防いでくれました。
しかし、海ごみ問題は尋常ではなくて、毎年800万トンものプラスチックが海に流出し、2050年には魚よりも海ごみのほうが多くなる、そんな悲観的な予測があります。だれも望んでいないそんな未来に何ができるの?
ごみと思えばごみだけど、ごみを資源と捉えればごみは減らせるかもしれない。
そう願って、プラスチックごみを素材にしたアップサイクル体験です。

プラスチックごみの現状、環境や生き物に与えてしまう影響などをまずはご紹介。

実際に、海洋プラスチックが落ちている環境を再現するために、砂浜に見立てた中に落ちているプラスチックごみを拾ってもらいます。
(この砂は、本当に愛知県内の砂浜からかき集めてきたものです、ひーひーでした笑)さあ、それでなにを作ったのか、というと、こちら。



もう、おわかりですよね。


会場の至る所で上を向いている人。
わー、きれい、と声が聞こえてくる。
万博キャラクターの〇〇に見える~、どれどれ、見せて~~~。捨てればごみになるプラスチックごみを、細かく刻んで万華鏡にしてみました。
いつの日か、訪れると思うんです。
『あれ、この万華鏡、なんだっけ』って日が。見た目では忘れていても、のぞいたら思いだしてもらえると良いな。
『あ、これ、あの日、プラスチックごみから作ったやつだ』って。
万華鏡の中に広がるキラキラした世界と、記憶がつながってくれれば、きっと、ごみのことを、環境のことを、気にしてもらえると思っています。万華鏡のほかには、キーホルダーやブレストレットも作りました。


キーホルダーは力仕事です。




キーホルダーだって、ブレスレットだって、巷で簡単に買えるし、それそのものがごみになっています。
今回は、つくる工程を自分で、お父さんやお母さんと、お子さんと、一緒にやったということが、そこに価値を生み、かつ、それが一緒にごみについて考えた、そういう機会から生まれたものだとしたら、きっと大切にしてもらえるであろう、いやいや、してもらえたらいいな、そんな風に思います。
ごみをごみとして見れば、それはごみ。
ごみだけど、これなにかできないかな、と思えば、ごみじゃない。
生み出せたのであれば、それは資源。今回使ったプラスチックごみは、決して自治体の分別に沿って集まったモノではなくて、自分たちで海で拾ったプラごみ、日常生活の中で分けたプラごみなど。
もちろん普段暮らす街の一員としての分別は必要だし、しないとごみ出しできないけれど、『これは資源かも』と思える、意識の分別とでもいうのでしょうか、そういうものが広がっていくと良いなって思います。
午前中に川で活動したのも意味があって、あそこでごみをいっぱい拾ってもらえました。
濡れていたり、汚れていたりするから、すぐに午後のアップサイクルには使えないんだけど、でも素材はこういうものです、という説明をすることができました。
そして、川で拾わなかったら海で細かく破砕して、それを海の生き物がエサと間違えて食べてしまったかもしれないし、それは川でも起きていくかもしれない・・・生き物とプラごみの関係や影響を実体験として持ってもらえたんじゃないかなって考えています。「森と川と人をつなぐ楽校」
モノづくりを通して、楽しみながら、川と自分が、そして、その先にある海と自分が、つながってもらえたんじゃないかなって思っています。万華鏡を「じっくり」と見つめてみるとキラキラ輝く中の世界。
そのキラキラを生み出すのは、海に落ちていたプラスチックごみ。
七変化するその美しさと輝きを見て、思ってもらえると嬉しい・・・「ごみじゃない」って。
そうやって、気づきが生まれると、意識に、行動に変わり、きっと社会も、環境も、もっと良くしていけると願っています。そんな願いと想いを持ち続けながら、これからも「じっくり」環境に向き合っていこうと思った、この日でした。



こんなに楽しそうな笑顔が、生まれる環境学習を、楽しんで、これからも。
ひろがっていきますように。この取り組みは、公益財団法人河川財団の河川基金の支援を受けて実施しています。
カラー-1024x563.png)
 岡本亮太(たんたん)が書いた記事
岡本亮太(たんたん)が書いた記事

CWPオリジナルLINEスタンプできました!25/12/02
念願かもしれない!やりたかったことができたかもしれない! そんな想いです。CWPオリジナルのLINEスタンプができました~!! https://line.me/S/sticker/320...

出前授業「自分の地域には、どんなごみが落ちているの?」を実施しました。25/11/04
名古屋市内の小学校4年生向けの出前授業です。 小学校で、地域の河川に出向いて生き物観察をしたら、予想外に子どもたちが、川のごみが多いことに関心を示したため、ごみについて学ぶ機会を、とい...

「森と川と人をつなぐ楽校」 ”おなじ”と”ちがい”25/10/07
今年度の環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」の最終回を、10月5日におこないました。 もともと予定していたのは、いつものと川とちがう川と、2つの川に出かけてガサガサしてみて、”おなじ”や”ちがい...
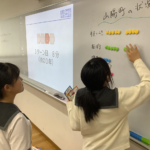
私立中学校にて、海ごみ問題の環境学習をおこないました。25/09/30
第21回日本水大賞。 かれこれ、6年前、2019年の出来事です。CWPが日本水大賞未来開拓賞を受賞した際の大賞を受賞されたのが、とある私立学園さんでした。当時は女子校でしたので、彼女たちの取り...

「森と川と人をつなぐ楽校」川と足元、生き物をじっくり見よう!25/09/12
じっくり。じっくり。 つかまえた!生き物捕まえた!という、あの興奮から、その先にある「その生き物こと、じっくり見てみよう」をやりました。加えて、足元もじっくり見てね。川の周りもじっくり見てね。...

【依頼案件】エコツアー実施しました!25/08/12
自主企画ではなく、ご依頼いただいた環境学習の講師を務めました。 フィールドは、湿原と河川です。湿原では、湿原に生息する生き物(魚や水生昆虫など)を通して、湿原の価値や生き物の生態を知ってもらう...

「森と川と人をつなぐ楽校」森を知ろう!森を感じよう!25/07/14
森と自分の距離感。そんなこと、考えたことある人って、どれくらいいるんでしょうね。 距離感って、なに?って、言われそうですけど、当たり前なことほど、自分に身近だと思うことは、距離が近いよ...

「森と川と人をつなぐ楽校」開校!25/06/30
2025年度から、新たな取り組みとしてスタートさせたのが環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」です。その記念すべき、最初の実施を、6月29日におこないました。 まずは、こちら。楽校のロゴができまし...
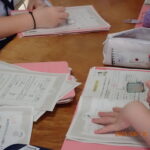
中学生の「環境を仕事にするって、どういうこと」の受け入れをおこないました。25/06/20
キャリア教育の一環で、環境分野に興味を持ってくれている中学2年生が、CWPを訪れてくれて、お話しする機会をいただきました。 自分たちで、CWPを調べ、どうやって行くかを調べ、質問や聞きたいこと...

2025年 WORLD CLEANUP DAYについて25/06/02
世界中で、みんなで、清掃活動を実施しよう!エストニアから始まった、WORLD CLEANUP DAY(WCD,ワールドクリーンアップデイ)は、2025年も実施されます。 ClearWa...