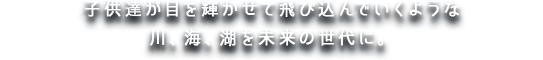CWPブログ
- 2025/07/15
-
「森と川と人をつなぐ楽校」森と川と虫の関係を知ろう!
執筆者: 堀川優貴子 (ゆっきー)

ライトトラップによる昆虫観察
ライトトラップというのをご存じですか?暗いところで強い光を当てて、昆虫を集める方法のことです。知ってるけど実際にやったことはない、という人も多いかもしれませんね。今回はその「ライトトラップ」を使って「森と川と人をつなぐ楽校」初、夜の部の観察会を開催しました!
「森と川と人をつなぐ楽校」で昆虫観察?と不思議に思う方もいるかもしれません。「怖い」「苦手」と思われがちな昆虫ですが、生き物の中で一番多いのが昆虫。環境や多様性を考える上でもとっても大切な存在なんです。だからどうしても昆虫にスポットを当てたプログラムを実施したかった。そして昆虫大好きな私としては、観察を通してその昆虫の「おもしろい」一面を知ってほしい、できれば触れ合ってほしい。なぜなら、そんな体験が自然環境や命のつながりを感じるきっかけとなり、自然を大切に思う心を育てると思うからです。
森や川にくらす多様な昆虫に出会うことで、環境に目を向け自然の大切さを実感してほしい。そういった思いから、今回「森と川と人をつなぐ楽校」で昆虫観察を実施するに至りました。
観察会スタート
会場「道の駅つくで手作り村」*。19時に全員集合!しました。
*今回特別にお願いして実施させてもらいました。普段はライトトラップや昆虫採集などはご遠慮いただきますようお願いします
まずは「ライトトラップってどんなもの?」「どんな昆虫が来るのかな?」といったお話でひと盛り上がり。「今日は何種類の昆虫が見つかるかな?」「5種類は見つけたいな!」などみんなで目標を立てて、いざスタート!
でも相手は自然。天気や気温のちょっとした条件の違いで、昆虫の集まり方はガラッと変わります。実際にどれだけの昆虫に出会えるかは、我々スタッフにも分かりません。
そんなワクワク・ドキドキを胸に、いよいよ観察のはじまりです。
ミニ・ライトトラップの設置
19時といってもほんのり明るい時間帯。そこでまずは懐中電灯片手にみんなでミニ・ライトトラップを設置しに行きます。

施設内を歩きながら、「どこに仕掛けたら昆虫が集まるかな?」と、設置場所をみんなで考えました。
ミニ・ライトトラップはこんな場所に置きました:
- 周りが開けた草むら
- 樹が多い遊歩道
- 木のすぐ下
それぞれの場所で、どんな昆虫が来るかは、夜になってからのお楽しみ!

ライトトラップの観察
すっかり暗くなってきた頃、お待ちかね!設置してあったメインのライトトラップの所に行ってみると・・・コガネムシやカゲロウなど、たくさんの昆虫たちが集まっていました!
「これ見たことある!」「これ何!?」「初めて見る!」と、みんな夢中で観察。説明なんていらないくらい昆虫に釘づけ。すごい集中力でした。

やってきたのは目標の5種類を大幅に超える昆虫たち。観察ケースに入れてじっくり観察したり図鑑で調べたり。やってきたのはなんていう昆虫かな?


今回は観察会なので、観察後の昆虫はすべて自然に返しています
昆虫がなぜここに来たのか?を考える
「この昆虫は普段どこにいるの?」「どうしてこの場所に来たの?」――そんな疑問から、森や川と昆虫たちのつながりについても考えてみました。昆虫といえば、森の中や草むらにいるものと思われがち。でも実は、川と深く関わる昆虫もたくさんいます。たとえばカゲロウやカワゲラ、トビケラの仲間などは、幼虫のときは川の中で暮らし、水の中で育ってから、成虫になって空を飛ぶのです。そういった昆虫がライトトラップに集まってきたとき、「この虫は川の中で生まれ育ったんだ」と気づくことで、水の中の世界へも想像が広がっていきます。
昆虫を通して森を見る。草を見る。そして川を見る。そんなふうに、自然を一つのまとまりとして感じ、いろんな命がつながって生きていることに気づいてくれたら。昆虫をきっかけに、「森」や「川」に興味を持ってもらえること。それがこの観察会を通して届けたかったテーマでもあったのです。
また、昆虫と光の関係についてもお話ししました。どうして光にあつまるの?といったところから、月の光との関係、青いライトがなぜ効果的なのか、光の種類によって集まる昆虫の数が違うことなどを紹介しました。
今回は比較としてLEDライトも設置しました。紫外線ライトとは昆虫の集まり方が驚くほど違う!ということも実際に見てもらい、「だから最近のコンビニや家の周りにはあまり虫が来ないんだね」という話にもつながりました。「どうしてここに来たのか」「なぜ集まるのか」といった背景を知ることで、興味がより深まり、身近な環境を新しい視点で見られるようになってくれたらと思います。

ミニ・ライトトラップをチェック
一通りメインのライトトラップ観察で盛り上がった後、みんなで設置したミニ・ライトトラップの観察に行きました。道中も「さっきあっちにもいた虫がここにもいる」「これキマワリだよね」「あ、コフキコガネがいたよ!」と、みんな昆虫博士さながらです。
設置したミニ・ライトトラップの結果は・・・
- 草むら → バッタや蛾がたくさん。コガネムシはほとんど来てない。
- 樹が多い遊歩道 → コガネムシがいっぱい!
- 樹の真下 → バッタや蛾のほかにもコガネムシがたくさん!
何とも面白い違いですね。周りに何があるかによって、集まる昆虫が違うんだって体感できたんじゃないかなと思います。そして観察途中には面白いハプニングも。途中でなんと、バッタをくわえたヤモリを発見!バッタは食べられちゃいましたが、これも生態系の一部。みんなで見守りました。
クライマックス
イベントの終盤、再びメインのライトトラップに戻ると、そこには今日一番の昆虫たちの大行列!沢山の種類のコガネムシ、大きなカワゲラやガガンボ、なんとクワガタまで!大人も子供も参加いただいた方もスタッフも関係なく、テンションMAXの大観察会です!私、ゆっきーも一緒になって大はしゃぎしてしまいました^^
みんな夢中になって、時間いっぱいまで観察しました。


最後に
今回のプログラムを通して、個人的にいちばん心を動かされたのは、子どもたちが昆虫と向き合うときのまっすぐな集中力です。目を輝かせてのぞきこみ、そっと手を伸ばし、夢中で観察する姿に、こちらのほうがハッとさせられました。今回のテーマは「多様性」や「環境と生き物のつながり」を感じてもらうことでしたが、それを一番雄弁に語ってくれたのは、間違いなく昆虫たちだったと思います。私たちがどれだけ言葉で伝えようとしても、子どもたちは「体験」から学んでいく。命が動いていること、生きもの同士がつながっていること、そしてその背景にある森や川という環境の尊さ。そういったことを、肌で感じ取ってくれたはずです。
この観察会が、子どもたちの心に、小さくても確かな「気づきの種」をまくことができたなら、それだけで大きな意味があったと感じています。そして、その種がやがて芽を出し、森や川、命のつながりを大切に思う気持ちへと育ってくれたら、こんなにうれしいことはありません。
余談ですが…解散後、会場を片付けていたらゾウムシがひょっこり登場。みなさんに紹介できず残念でした。でもこれもまた自然。さっきいまでいなかった昆虫がひょっこり現れて、今日出会えた昆虫たちも明日は出会えないかもしれない。そんな一期一会も、自然ならではの楽しさのひとつですね。

※このプログラムは、公益財団法人河川財団の河川基金のご支援を受けて実施しています。
※「道の駅つくで手作り村」でのライトトラップや昆虫採集などはお控えいただきますようお願いいたします。
 堀川優貴子(ゆっきー)が書いた記事
堀川優貴子(ゆっきー)が書いた記事

「森と川と人をつなぐ楽校」森と川と虫の関係を知ろう!25/07/15
ライトトラップによる昆虫観察 ライトトラップというのをご存じですか?暗いところで強い光を当てて、昆虫を集める方法のことです。知ってるけど実際にやったことはない、という人も多いかもしれませんね。...

豊田市広沢川「川の思い出を語ろう!」を開催しました20/11/25
広沢川ふるさとの川づくりの一環で、昔の川の思い出を語るワークショップを開催しました。 豊田市では、荒れてしまい、人が近づかなくなった小川を、地域住民による多自然川づくりによって、地域に愛される「...